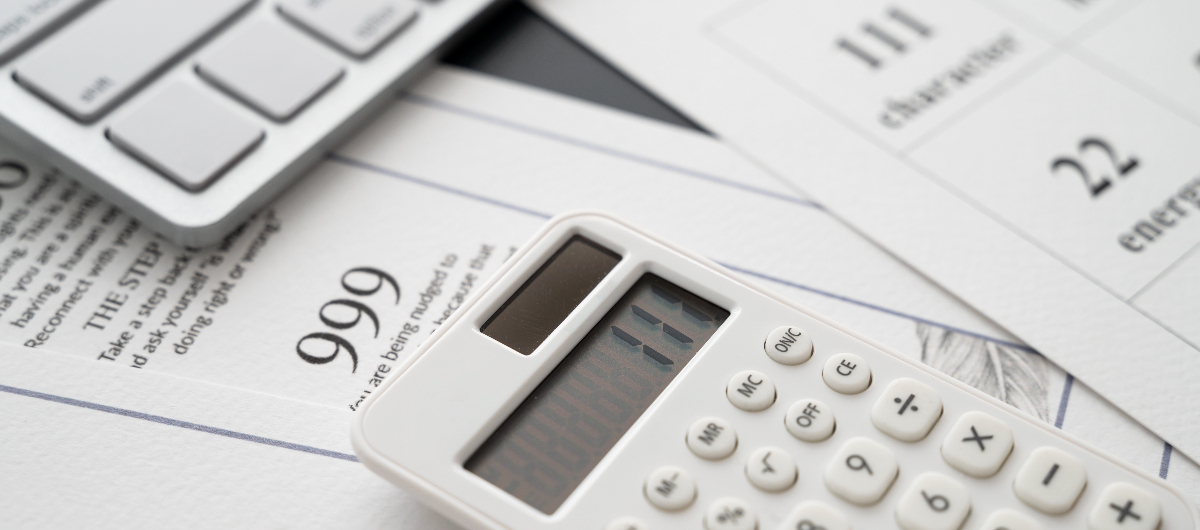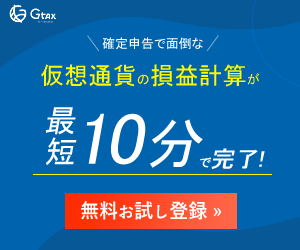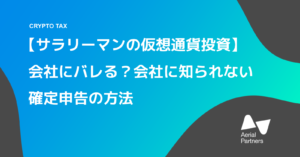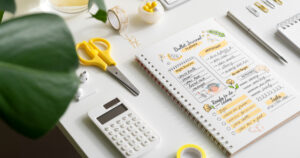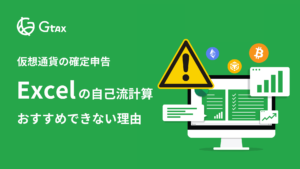確定申告の時期に必要となる暗号資産(以下、仮想通貨)の「取得単価」。
しかし、取引履歴の場所がわからなかったり、以前に取引していた仮想通貨取引所が閉鎖してしまったりといった理由で取得単価が分からず、困ってしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、仮想通貨の取得単価がわからなくなってしまったときの対処法や計算方法、それから仮想通貨の確定申告において必要な基礎知識を解説します。
仮想通貨の取得単価が必要となるのはなぜ?
そもそも、仮想通貨の取得単価はなぜ重要なのでしょうか。
その理由は、私たちが支払う税金の計算に必要な「所得」を確定するときに、取得単価が必要となるためです。
仮想通貨を売却した際の利益、つまり所得となる価額は「取得単価×数量」で計算されます。
上記のように、所得額は「売った価額から、売った分の取得単価を差し引く」ことで計算することができるため、取得単価が分からないと、確定申告に必要な計算を進めることができません。
確定申告は暗号資産から得た所得が20万円を超えた人を対象に義務付けられており、取得単価を把握することはとても重要なことといえます。
仮想通貨の平均取得単価の計算法は2種類
仮想通貨の取得単価の計算方法には、以下の2種類があります。
- 総平均法
- 移動平均法
原則として個人は総平均法、法人は移動平均法を使って取得単価を計算します。
ここからは総平均法、移動平均法について解説しましょう。
総平均法
総平均法とは、期間全体(1年間)の取得総額を、所有している仮想通貨の数で割って計算する方法です。
ケーススタディとして、以下の価額で1BTCずつ計3回購入した例で考えてみましょう。
- 100万円で購入
- 200万円で購入
- 300万円で購入
上記では購入額の総額が600万円となり、総平均法の場合は所有した総数(3BTC)で割ることになるため、1BTCあたりの単価は200万円となります。
取得価額を全部足したものを最終的に所持している総数で割るだけなので、計算が簡単というメリットがありますが、途中で売却しても平均単価を確定させることができないので、計算上の利益額がわかりにくいというデメリットもあります。
移動平均法
移動平均法は、仮想通貨を購入するたびに平均取得単価を計算する方法です。
総平均法の項目と同様に、1BTCずつ購入した例を見ていきましょう。
移動平均法では以下のように算出します。
- 100万円で購入(100万円)
- 200万円で購入(300÷2BTC=150万円)
- 300万円で購入(600÷3BTC=200万円)
※()内は計算された取得価額
移動平均法は購入の都度「現在いくつ保有しているか」「現時点での総額はいくらか」を再計算し、取得価額を割り出す方法です。
また途中で売却した場合は、売却直前の平均単価を使って所得額を計算します。
総平均法と異なり、都度計算するために利益を把握しやすいというメリットがあります。
しかし、その分作業の手間がかかり、誤っていた際には初めから見直さなければならないといった作業に関するデメリットも存在します。
個人は原則として総平均法を使用して計算しますが、税務署に届出を提出することで移動平均法に変更することができます。
平均取得単価の計算法については以下でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
仮想通貨取引の移動平均法と総平均法の違いを図解でわかりやすく解説
仮想通貨の取得単価を知る方法
前述のように、仮想通貨の所得額を割り出すにはまず「取得価額」を知り、そのあと総平均法や移動平均法を使って取得単価を計算しなくてはなりません。
それでは、取得価額はどのようにして知ることができるのでしょうか。
ここからは取得価額を知る一般的な方法を2つ解説します。
仮想通貨取引所の年間取引報告書や取引履歴をダウンロードする
仮想通貨の取得価額の多くは、仮想通貨取引所のHPからダウンロードできる「年間取引報告書」や「取引履歴」に記載されています。
ただし各取引所によりフォーマットが違い、また1つの書類だけでは情報が不足することもあるため、必要な書類を入念に確認しましょう。
下記の記事では、取引所別に取引履歴をダウンロードする方法や取得単価の計算に必要な書類一覧をまとめています。
ぜひご自身の取引所を確認し、ダウンロードにお役立てください。
【完全保存版】主要仮想通貨取引所の取引履歴ダウンロード方法まとめ
銀行・仮想通貨口座の記録を確認する
取引所が無くなってしまった、取引履歴が残っていないなどの理由で取得単価が分からない場合は、銀行・仮想通貨の口座やウォレットの出金記録から、取得単価を推測することができます。
ただし、銀行口座からの入金は通常仮想通貨口座を仲介するため、出金額と取得価額と同じになるとは限りません。
その場合は出金日からその日の暗号資産のレートを確認することで、推測して算出することができます。
仮想通貨の取得単価がわからないときは「みなし取得価額」を活用
仮想通貨の取得単価がどうしても分からない場合は、「売却した金額の100分の5相当(5%)」を取得価額として計上してもよいとされています。
この場合の計算式は「収支=売却金額-(売却金額×0.05)」となります。
何らかのツールを使って仮想通貨の損益を計算をしている場合でも、みなし取得価額の適用方法を確認しておくと、いざというときに慌てずに対処することができます。
実際に、計算例で見ていきましょう。
①取得額が不明な1BTCを500万円で売却したとき
それでは、実際に所得額を計算してみましょう。
取得価額が不明な仮想通貨(1BTC)を500万円で売却した場合は以下のような計算式になります。
500-(500×0.05)=500-25=475万円
上記から、取得価額は25万円、所得は475万円と計算することができます。
②複数回売買のうちに購入額不明分があるとき
- 購入額不明(1BTC)
- 200万円で購入(1BTC)
- 400万円で購入(1BTC)
- 500万円で1BTC売却(‐1BTC)
上記のように複数回の仮想通貨の購入・売却を行う中で、一部の購入金額が不明な場合、その計算方法については国税庁や税法において明確な指針は定められていません。
該当する購入や売却については、不明分を他の取引から分離し、5%のみなし取得価額を使って計算するなどの個別の対応が考えられます。
ただし、具体的な対応方法は、個別状況によって異なるため、税務署や税理士に相談することを強く推奨します。
まとめ
仮想通貨の「取得単価」は、確定申告時に所得額を確定する際に必要なもので、「取得価額」を使って算出します。しかし仮想通貨の取得価額が分からないと、肝心な取得単価も分からず、つい焦ってしまうかもしれません。
しかし、どうしても分からない場合でも「みなし取得価額」を活用すれば取得単価を計算することができます。
仮想通貨の確定申告では取引方法によってさまざまな規定があるため煩雑になりやすく、混乱してしまうこともあるかもしれません。
楽に確定申告の手続きを進めるためにも、取引履歴は定期的にダウンロードし、適切なツールや専門家の力を借りて行うと安心です。
Gtaxでは仮想通貨における確定申告を解説したコラムを掲載しているため、ぜひチェックしながら進めてみてください。