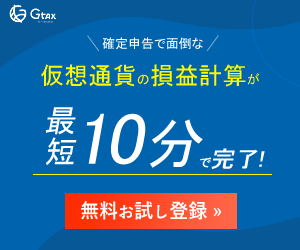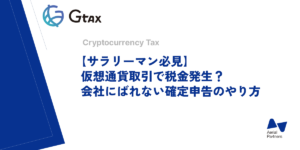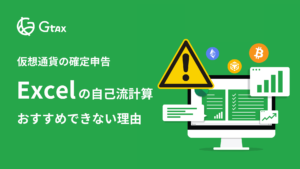暗号資産(以下、仮想通貨)取引に限らず、確定申告が必要な方の申告漏れが毎年数多く発覚しています。納税は国民の義務ですが、確定申告の知識不足や「バレない」「大丈夫」という軽い考えで放置している方もいるようです。
無申告がバレるとペナルティが発生し、場合によっては本来納める税金以上の課税が課されます。知らずに申告期限を逃したり、未申告が発生したりすることのないよう、確定申告が必要になる人の条件や、罰則の詳細をチェックしておきましょう。
仮想通貨の確定申告をしなかったらなぜバレる?
仮想通貨取引で一定以上の利益を得ると所得税が発生し、基本的には確定申告が必要になります。
個人や法人の申告漏れや過少申告は、あらゆる方法で厳しくチェックされています。
それぞれバレてしまう要因を詳しくみてみましょう。
仮想通貨取引所への税務調査によってバレる
仮想通貨の申告漏れが発覚する主なルートとなっているのが、仮想通貨取引所への税務調査です。
税務署は会社・個人に関係なく、きちんと納税されているかを確かめるため税務調査を行っています。仮想通貨においても、取引履歴からどのくらい利益を得ているのかが一目瞭然です。申告漏れがあれば、すぐにバレてしまうでしょう。
また、自分が調査対象ではなくても取引先や関連会社などに税務調査が入り、自身の無申告や申告漏れが発覚するケースもあります。
SNSの投稿でバレる
不特定多数に向けて自身を発信できるSNSは、同時に税務署のチェックも入りやすく、申告漏れを発見されるケースが増えています。
SNSでは大きな利益を得た方がインフルエンサーとなり、大きな注目を集めているケースも少なくありません。しかし匿名アカウントでも、税務署の調査が入れば身元や取引履歴はすぐに明らかになってしまいます。売上に対する言及はなるべく避けたほうが安心できるでしょう。
銀行口座の動きでバレる
税務署は、申告漏れが疑わしいと思われる人物の銀行口座の動きをチェックできます。この場合、調査は税務署と銀行との間で行われ、申告する側は知らないまま調査が進められます。
銀行口座の取引履歴はごまかしが効かず、近年はオンラインでも迅速に確認できます。申告漏れがあれば、出入金の流れからすぐに発覚してしまうでしょう。
仮想通貨の確定申告をしなかった場合の罰則は?
確定申告をしなかった場合、本来納めるべきだった所得に最大14.6%の延滞税がかかるほか、ペナルティとして課税された金額も追加で納める必要があります。追徴課税の種類は、次の4つです。
- 無申告加算税(最大30%)
- 過少申告課税(最大15%)
- 重加算税(最大50%)
- 不納付加算税(最大10%)
確定申告を怠ったことがバレると「延滞税+無申告加算税」や「延滞税+重加算税」といったように延滞税とペナルティの課税が重なり、大きな金額となってしまうので注意が必要です。罰則ごとに課税割合や内容が異なりますので、一つひとつ解説していきます。
無申告加算税
無申告加算税とは、確定申告の漏れや遅れが故意ではない場合に発生するペナルティです。課税額は納税するタイミングと、納付すべき金額によって異なります。
| 納税するタイミング | 税率 |
| 税務調査の通知前(自主的に申告した場合) | 5% |
| 税務調査の通知~更生・決定の予知前 | 10%(15%*1) |
| 税務調査による決定があった場合 | 15%(20%*2) |
参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
また、過去5年以内に無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがある場合は、表の税率からさらに10%上乗せされ、最大30%の税率になります。
過少申告課税
過少申告課税とは、期限内に確定申告はしているものの、納める税金が少ない場合に加算されるペナルティです。仮想通貨での所得を少なく申告しているのがバレてしまったときに課税されます。納める所得税に対し、課される税率は次の通りです。
| 納税するタイミング | 税率 |
|---|---|
| 税務調査の通知前(自主的に申告した場合) | 課税されない |
| 税務調査の通知~更生・決定の予知前 | 5%(10%*2) |
| 税務調査による決定があった場合 | 10%(15%*3) |
(*2)(*3)納付すべき税額が50万円を超える場合には、その超える金額について適用される税率
参考:国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
税務調査の通知をそのままにしてしまうと、最大15%の税率が課されてしまいます。
重加算税
重加算税は、確定申告漏れや所得を少なく申告した場合において、「隠ぺい仮装行為」にあたるケースだった場合に課税されるペナルティです。明らかな利益があるのに意図的に確定申告せずにいたり、他人名義の口座を使って仮想通貨の取引を行っていたりするような悪質なケースが当てはまります。
納税額はもともと対象となっている加算税の種類によって異なり、次の通りです。
| ペナルティの種類 | 税率 |
|---|---|
| 過少申告加算税・不納付加算税 | 35% |
| 無申告加算税 | 40% |
過去5年以内に無申告加算税、もしくは重加算税を課されたことがある場合はさらに引きあがり、税率は50%となります。本来支払う予定の所得税に加え、大きな税率が課されてしまうでしょう。
不納付加算税
不納付加算額とは、給料から天引きされた源泉所得税の納付が遅れた場合に、会社側に発生するペナルティです。本来、源泉徴収税は給料日の翌月10日までに税務署に納付しますが、遅れてしまうと延滞税だけでなく不納付加算税が課される可能性があります。
仮想通貨取引では直接の影響はありませんが、この場合の税率も参考までにお伝えします。
| 条件 | 税率 |
|---|---|
| 納付期限から1ヶ月以内に納付した場合災害や通信障害などの理由で納付が困難だと認められる場合 | 課税されない |
| 納付期限後、自主的に納付した場合 | 5% |
| 税務署から通知を受けてから納付する場合 | 10% |
税務署から会社が未納の通知を受けてからの納付になると、最大10%の税率が課されてしまいます。
仮想通貨取引について「確定申告するべき人」とは
一定以上の収入があるにも関わらず、所得を隠したり税務署からの通知を放置していると、重たいペナルティが発生します。悪質な隠ぺい仮装行為はもちろん、「バレないだろう」と軽い気持ちで確定申告を怠ったケースも同様です。
仮想通貨で一定以上の利益がある方は、必ず確定申告をしなくてはいけません。うっかりや勘違いで後々ペナルティが発生しないように、確定申告が必要になる条件をしっかりとおさえておきましょう。
確定申告するべき人は、次の2パターンです。
仮想通貨取引で年間20万円超の利益が出た人
ひとつ目の条件は、仮想通貨の取引で年間20万円以上の利益を得た場合です。
給与所得者は会社を通して年末調整を行っているため、個人での確定申告は基本的に不要です。済んでいます。しかし、年末調整には仮想通貨での利益が含まれず、給与以外の所得が一定を超える場合は確定申告する必要があります。
ここで注意してほしいのは、「20万円とは、銀行口座に振り込まれた金額ではなく、経費などを引いた所得額」ということです。具体的には、次の計算式で求められます。
所得=仮想通貨の売却価額 – 1単位当たりの取得価額(手数料込)× 数量
また、仮想通貨は売却時だけでなく、以下のようなケースでも所得が発生します。
| 所得が発生する条件 | 所得の計算式 |
|---|---|
| 仮想通貨をほかの仮想通貨と交換した場合 | 購入する仮想通貨の価格-売却する仮想通貨の取得価額 |
| 仮想通貨決済で商品やサービスを購入した場合 | 決済した購入価格-1単位当たりの取得価額(手数料込み)×数量 |
異なる仮想通貨への交換や商品やサービスの購入は、銀行口座に振り込まれていなくても「一度利確した所得」とみなされます。すべての所得を合計し、年間20万円を超える方は、必ず確定申告を行ってください。
給与所得や退職所得以外の所得金額が年間20万円超の人
確定申告が必要なもうひとつの条件は、給与所得や退職所得以外の所得が年間20万円を超える場合です。
所得税には、仮想通貨が含まれる「雑所得」以外にも「事業所得」や「不動産所得」などいくつかの種類があります。所得税は、すべて合計した金額に所得税が課される総合課税となるため、仮想通貨での所得が20万円以下でも、場合によっては確定申告が必要になるのです。
最近では個人で副業を行っている人など、本業以外の収入がある方も増えています。仮想通貨以外に所得を得ているなら、それらの合計額が年間20万円を超えていないかしっかり確認してください。
また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする方は、仮想通貨取引の所得が20万円以下の場合も申告が必要となるため注意しましょう。
まとめ
仮想通貨取引では、得た利益が一定の金額を超えたら確定申告が必要です。無申告やごまかしは税務署によってチェックされ、過去に遡って重たいペナルティが課されてしまいます。どのような場合に確定申告が必要なのかしっかりと把握し、漏れなく確定申告を行いましょう。