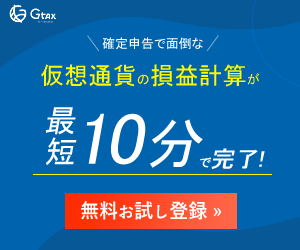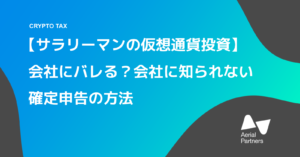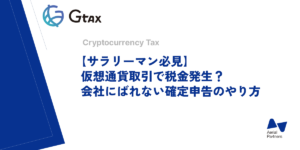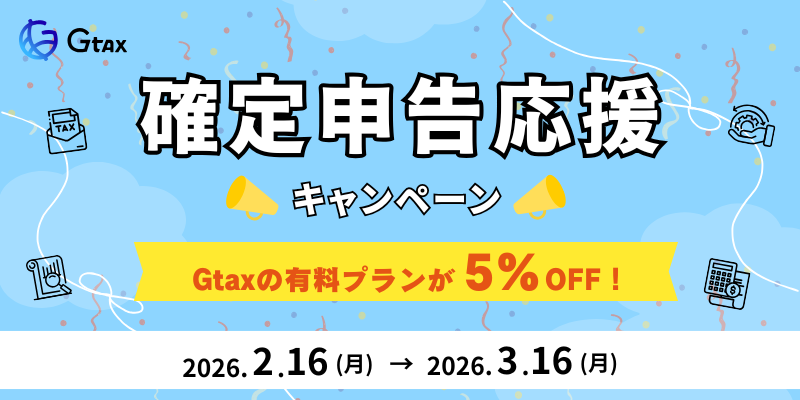仮想通貨取引で利益が出ると嬉しいもの。しかし、利益が出たら必要になってくるのが納税および確定申告です。
納税額は出た利益から経費を差し引き、確定申告を行うことで決定されます。
では、節税に直結する「経費」にはどのようなものがあるのでしょうか。
本記事では仮想通貨取引の経費にできる支出やそのコツ、節税効果のある所得控除について解説します。
所得とは「収入から経費を差し引いたもの」
確定申告では総収入から経費を差し引いた額(所得)に税率をかけて計算します。
「経費を制する者が制す」といっても過言ではないともされています。
確定申告において総収入を減らす方法は限定的であるものの、必要経費は認められている範囲内なら算入することができます。
経費計上できるものを知っておくと納税額の減少が期待できるため、どんな支出が「経費」として認められるのか、本記事で一緒に確認していきましょう。
仮想通貨取引に関して全額を経費計上できるもの
仮想通貨の取引に直結する支出は、全額を経費として計上することができます。
ここからは仮想通貨の確定申告で必ず押さえておきたい「支出の全額を経費として扱えるもの」を紹介します。
仮想通貨の取得費(取得価額)
仮想通貨の取得費は、仮想通貨の確定申告であれば必ず算入が必要となる経費です。
ここでいう「取得費」とは仮想通貨を取得(購入)したときの金額のことをいいます。
今回は1BTCを100万円で購入し、150万円で売却した例を考えてみましょう。
上記の例では購入した額である100万円が経費となり、差額の50万円が所得となります。
計算式は以下の通りです。
150万円(売却費)‐100万円(取得価格)=50万円(所得)
売買を1度だけ行ったケースでは、上記のような計算式となります。
しかし、仮想通貨の取得費は算入方法にはルールがあり、領収書の額をそのまま計上するといった経費とは違う特殊な扱いとなります。
1年間で複数回売買を繰り返した場合、原則として個人は「総平均法」、法人は「移動平均法」を使って計算する必要があるため、注意が必要です。
取得費の計算方法については以下の記事で解説しています。
仮想通貨取引の移動平均法と総平均法の違いを図解でわかりやすく解説
取引手数料や送金手数料など
仮想通貨の取引では、以下のような手数料がかかることがあります。
- 取引所に円を送金した際の「送金手数料」
- 仮想通貨を売却するときに支払う「売却手数料」
- 仮想通貨を取得するときに支払う「取得手数料」
上記のような手数料は全額、必要経費として算入することができます。
しかし、仮想通貨を取得した際にかかる「取得手数料」のみ、前項で解説した「取得費」のなかに含めて計算するため、留意しておきましょう。
例えば、「100万円で仮想通貨を購入し、2,000円の取得手数料を支払った」という場合では、合計した100万2,000円が「取得費」となります。
こちらの金額は前項のように「総平均法」か「移動平均法」で計算することになるため、確定申告時は確認しながら進めていきましょう。
書籍代、セミナー代
仮想通貨の取引のスキルアップにかかる「書籍代」や「セミナー代」も、全額経費として扱うことができます。
書籍代は書店から購入した紙媒体だけでなく、電子書籍なども対象です。
そのため、書籍の購入時やセミナー参加時は必ず領収書をもらい、安全な場所に保管しておきましょう。
一方、書籍やセミナー代金が税務署に「仮想通貨取引とは関係ない」と判断された場合、経費として認められないこともあります。
仮想通貨の取引用に購入した電子機器
仮想通貨の取引専用として購入したパソコンやスマートフォン、追加のディスプレイも経費として扱うことができます。
なお、10万円以上の製品は減価償却の対象となるため、購入金額は数年間で分割され、一部のみ当年の経費として扱われます。
10万円以上の商品を購入したときはその年に全額を経費計上することはできないため、減価償却にて算入しましょう。
情報交換にかかった飲食代や交通費
仮想通貨の情報交換にかかった飲食費や交通費、駐車場代なども経費として扱うことができます。
ただ、経費となるのはあくまでも「仮想通貨関係の集まりで使った経費」であり、私用の飲食費や交通費を算入すると虚偽申請として扱われる可能性があります。
また回数によっては税務調査で疑われる要因にもなるため、経費計上のときはレシートや領収書のほか、仮想通貨関連の経費であることを証明できる記録を残しておくとよいでしょう。
確定申告に使うツール代、ソフト代など
仮想通貨の確定申告のために導入したツール代、セキュリティ向上のためのソフト代なども経費として算入することができます。
対象となるものには仮想通貨関連の情報を管理する会計ソフト、損益計算ソフト、記憶装置(SDDやHDD)など該当します。
仮想通貨取引に関して按分すれば経費計上できるもの
確定申告では「仮想通貨の取引に関係している出費」を経費として扱うことができます。
ただ、私用で使っているスマートフォンをそのまま取引にも利用するケースなどでは「一部関係、一部無関係」となり、支払いの全額を経費として計上することはできません。
一方、関係している部分は経費として扱うことができます。
このように関係している一部金額のみを経費として扱うことを「按分(あんぶん)」といいます。
按分では使用割合に応じて経費分を計算しますが、この割合は税務署に対して「仮想通貨に関係している出費である」と合理的な説明ができる必要があるため、考慮して計上しましょう。
ここからは、按分によって経費計上できるものを紹介します。
自宅兼事務所の家賃
仮想通貨の取引を自宅で行っている場合、自宅の家賃を按分して経費計上することができます。
このようなケースでは、取引に使っている場所(パソコンが置いてある部屋など)の使用面積で按分するのが一般的です。
自宅の全面積に対する使用面積の割合を計算し、その割合に応じた分の家賃を経費として算入することができます。
自宅兼事務所の光熱費
光熱費も按分して経費計上できる支出です。
しかし、光熱費は私生活でも消費するため、合理的な説明が難しい支出でもあります。
例えば、取引を行っている時間が10時間、そのうち部屋の電気やエアコンをつけているのが5時間だった場合、24分の5(約20%)を光熱費として扱える可能性があります。
とはいえ電子機器の充電やキッチン家具の電気代などもあわせると完璧に切り分けられるものではないため、詳しくは税理士と相談しながら決めるとよいでしょう。
PCやスマホ代、通信料
私用で使用しているPC代やスマホ代、通信料も按分の対象です。
仮想通貨の取引専用で購入したものは全額経費として計上することができますが、プライベートでも使用している場合は按分するとよいでしょう。
スマートフォンではアプリの使用時間が確認できるスクリーンタイムなどで仮想通貨関連アプリの使用時間を割り出すこともできます。
また通信費はインターネットを使用している総時間から、取引時間だけを切り出すことで使用割合を計算することができます。
仮想通貨関係のセミナーや食事代にかかる旅費交通費
仮想通貨関連のセミナーに参加するための費用は全額経費として計上することができます。
しかし「セミナーに参加したついでにプライベートで遊んだ」「会場が会社に近いので仕事のあとに寄った」など、プライベートが関わってくる出費であったときは仮想通貨に直接かかわってくる部分のみを経費計上しなくてはなりません。
前者のように、元々セミナーに参加する目的で遠出した場合は交通費を全額計上できるケースもあります。
また後者では「家から会社」の交通費は経費として計上できませんが「会社からセミナー会場」の交通費は計上できることもあります。
また、車移動をしたときは移動距離分のガソリン代を按分することも可能です。
経費だけではなく「所得控除」も活用できる
税金の計算に必要な「所得額」は、経費を算入することで減らすことができます。
そんな経費と同じくらい注目しておきたいのが所得控除です。
所得控除とは、個人の事情にあわせて所得額から一定額を差し引ける制度のことをいいます。
つまり、所得控除を利用することで「所得額」を減らすことができるため、経費と同様に節税効果が期待できます。
本項では、利用しやすい所得控除を3つ紹介します。
生命保険料控除
生命保険料控除では、支払った生命保険料の額に応じた一定額(最大4〜5万円)を所得から控除することができます。
また、生命保険料控除には2012年以降に契約したものを対象とする「新制度」と、2012年以前に契約したものが対象である「旧制度」があります。新旧で控除要件や金額などが変わってくるため、気に留めておくことが大切です。
- 新制度で対象となるもの
-
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
- 旧制度で対象となるもの
-
- 一般生命保険料控除
- 個人年金保険料控除
また、会社員として勤務している方は会社の年末調整によって控除されるため、特別な手続きは必要ありません。
医療費控除
医療費控除とは、1年間の医療費が10万円を超えた場合に受けられる所得控除です。
自身の疾病のみならず、生計を同一とする家族分の医療費も対象となります。
- 歯医者での治療・診療
- 健康診断・人間ドック
- レーシック手術
- 入院費
- ドラッグストアで買った医薬品(法律第2条第1項、医薬部外品などは対象外)
医療費控除は年末調整の対象外であるため、自身で計算・手続きを行う必要があります。
提出書類は国税庁のHPから入手することができます。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金は、共済契約に基づく将来のための掛金を支払った場合に適用される所得控除です。
小規模企業共済等掛金控除の対象となるものには以下のようなものがあります。
- 小規模企業共済の掛金
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金
- 企業型確定拠出年金の掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
小規模企業共済当掛金控除では、その年に支払った掛金の全額を控除することができます。
会社員は会社から渡される年末調整の書類に「保険料控除申告書」に申告欄があるため、そこに掛金の合計額を記載することで申請することができます。
まとめ
仮想通貨の利益から経費を差し引きたいとき、大切なのは「仮想通貨と関係している支出かどうか」という観点です。仮想通貨と関係している支出であればその多くを経費として計上することができます。
一方、無理やり仮想通貨と結び付けたような支出は経費とは認められず、税務調査で指摘される要因にもなります。
レシートや領収書を日頃からしっかり保管できる仕組みを整えられると安心です。
また経費を「雑費」として計上し過ぎると万が一税務調査が入った場合に詳しく聞かれてしまう場合があります。 そのため、経費については「旅費交通費」や「消耗品費」などきちんとした科目で仕訳を行うようにしましょう。
消耗品費と雑費の違いに関しては、下記「タックスナップ」のサイトで解説されている記事がより詳しくなっています。
参考:雑費と消耗品費の違いは?確定申告での仕訳例や注意点を確認
確定申告では、経費として認められる範囲内で、計上漏れの無いように手続きを進めていきましょう。