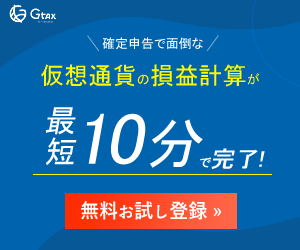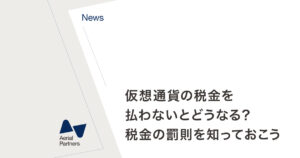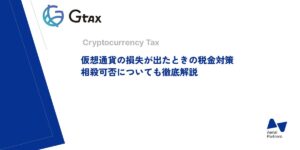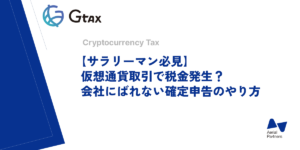仮想通貨の税金シミュレーター
こちらのシミュレーターでは源泉徴収票に記載されている給与額や社会保険料に加え、仮想通貨取引による利益や家族構成などを入力することで、ある程度どれくらいの税金がかかることになるのかを計算できます。
入力が一通り済んだら、下部にある「税金を計算する」ボタンを押すことで、その下に結果が表示されます。
税金計算シミュレーター
簡単入力で今年の税金をシミュレーション
仮想通貨の税金に関する基礎知識
仮想通貨の売買で得た利益や、ステーキング報酬・エアドロップなどの収益は、税法上「雑所得」に分類されます。
これは、給与所得や事業所得のように特定の区分に当てはまらない所得をまとめたカテゴリーで、会社員・主婦・学生・フリーランスなど、誰が得たものであっても同じ扱いになります。
雑所得は「総合課税」の対象となるため、仮想通貨の利益は給与所得など他の収入と合算して税額が計算されます。
その結果、仮想通貨の利益が増えるほど所得税や住民税が上がる仕組みになっています。
課税されるタイミングや確定申告のやり方など、仮想通貨の税金については下記で詳しく解説していますので、こちらも併せて読んでみてください。

税金計算に必要な要素と仕組み
税金は単純に仮想通貨取引で得た「利益」にかかるというものではなく、経費等を加えた「所得」に対してかかり、実際の計算では給与所得や社会保険料なども合わせる必要があります。
シミュレーターの計算結果がなぜこのような計算になるのか、ひとつずつ理由を解説していきます。
給与所得にかかる控除について
会社員の場合、毎月の給与から所得税が天引きされていますが、その際に適用されるのが「給与所得控除」です。
この控除は、勤務に必要な交通費や通信費、自己負担の経費などを一律に差し引く仕組みで、実際に領収書を集めなくても自動で計算されます。
控除される額は、次のように変わっていきます。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
例えば、給与所得が500万円における控除額は「500万×20%+44万=144万」となり、この額を引いた「356万円」が総所得として合算する際の給与所得の数字となります。
利益から経費を差し引いたものが所得になる
仮想通貨の所得を計算する際には、利益から「必要経費」を差し引くことができます。
必要経費とは、その所得を得るために実際に支出した費用のことで、代表的なものには次のようなものがあります。
- 取引所での売買手数料
- ブロックチェーンの送金(ガス)代
- ウォレットやトラッキングツールの利用料
- 税務計算ソフトの費用
- 会計・税務サポートに要した顧問料
ただし、パソコン代や電気代、通信費などのように私的利用と共通する支出を経費に入れる場合は、業務利用分のみを合理的に按分する必要があります。
「パソコン利用の3割を取引に使った」などの明確な根拠が求められるため、個人判断だけで大きく経費計上するのは避けたほうが安全です。
なお、経費計上は実質的な節税手段のひとつです。
経費を適正に計上することで、課税所得を減らし、税金負担を軽減できる可能性があるため、欠かさず行うようにしましょう。
配偶者・扶養控除は所得金額で変わる
配偶者控除や扶養控除は、家庭の所得状況に応じて税負担を軽減できる仕組みです。
ただし、これらの控除が適用されるかどうかは、「本人の合計所得金額」や「配偶者・扶養家族の所得」によって変わります。
たとえば、仮想通貨の利益によってあなた自身の所得が増えると、「合計所得が上限を超えてしまい、配偶者控除が一部または全て受けられなくなる」というケースがあります。
また、配偶者側に仮想通貨の利益がある場合も同様で、その金額が増えると「配偶者控除を受ける条件(年収95万円以下など)」から外れてしまうことがあります。
社会保険料には注意が必要
社会保険料(健康保険・厚生年金など)は、基本的に給与収入をもとに算定されます。
そのため、仮想通貨取引による利益が発生しても、すぐに保険料が上がるわけではありません。
ただし、確定申告を行うことで所得が増えると、翌年度の住民税が上がる場合があります。
特にフリーランスや自営業の方は、住民税をもとに算定される国民健康保険料や介護保険料が上昇する可能性があります。
一方で、会社員の場合は給与ベースでの社会保険料計算のため、仮想通貨の利益が直接影響することはほとんどありません。
仮想通貨の所得は「社会保険料を直接変動させないが、翌年の住民税を通じて間接的に影響する可能性がある」と理解しておくと良いでしょう。
確定申告後の住民税通知などで負担が増える場合もあるため、所得全体を見据えて計画的に取引を行うことが大切です。
仮想通貨の税金計算は「所得全体」で考えることが重要
仮想通貨の税金は、単純な売却益だけでなく、給与・扶養・控除・社会保険など、個人全体の所得構成によって大きく変わります。
特に、給与所得との合算課税や控除の変化は税額に直結するため、「なぜこの税額になるのか」を理解しておくことが重要です。
今回のシミュレーターは簡易版となっていますが、実際に仮想通貨の所得を計算する際には「総平均法」と「移動平均法」のどちらかを用いて正確に計算する必要があったり、NFTやDeFiの取引履歴をすべて洗い出す必要があったりなど、正しい所得額を算出するために複雑な作業が必要となります。
「Gtax」はそうした計算をなるべく簡素・自動で行える仮想通貨特化の計算ツールとなっていますので、特に初めて確定申告をすることになりそうな方や取引数が多くて計算に時間が取られるといった方はぜひご活用ください。