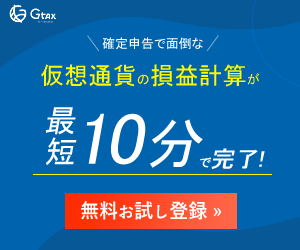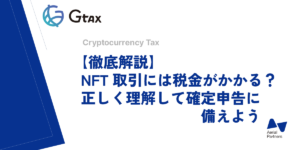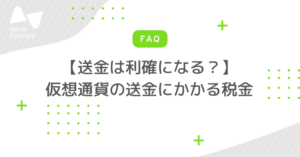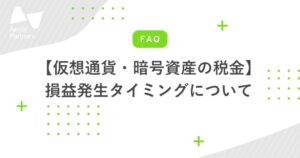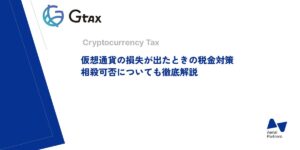仮想通貨投資をする中で、仮想通貨の購入の代行や家族への贈与など、単なる取引以外に第三者とやり取りをしたことがある人は少なくないのではないでしょうか?
自分自身の取引についてだけでも損益の計算は複雑ですが、第三者とのやりとりがあるとさらに複雑化します。
今回は第三者間のやり取りについて、贈与税の概要や計算方法を解説します。
仮想通貨(暗号資産)取引において第三者間のやり取り
一般的に、取引所以外の第三者と仮想通貨を取引するケースとしては、下記が主に考えられます。
- 家族を含む第三者への贈与
- 購入の代行・購入の委託
- 貸し借り
- 相対取引(取引所・市場を介さないで取引すること)
それぞれについて、税金額の計算上、問題となるポイントを挙げていきます。
ビットコインなど仮想通貨を第三者へ贈与する場合の税金
ビットコインを子供にあげるなど、第三者に対して、対価を受け取ることなく仮想通貨を贈与した場合、何らかの税金が課せられるのでしょうか?
仮想通貨は「財産」にあたると考えられており、家族などの第三者に対して贈与すると、仮想通貨を贈与した人に税金がかかることはりませんが(所得税法59条2項、60条1項2号)、一定額以上を受け取った人に対して贈与税が課されます(相続税法1条の4)。贈与税について、詳しくは国税庁HPをご覧ください。
国税庁:贈与税
もっとも、仮想通貨を受け取った人に贈与税が課されるのは、個人間で仮想通貨の贈与を行う場合に限られます。
法人から贈与を受けた場合や、法人に対して贈与した場合には、贈与を行った側・贈与を受けた側の双方について、所得税・法人税など、贈与税以外の点が問題となるため、専門家にご相談ください。
参考:仮想通貨(暗号資産)をそのまま相続すると二重課税になる?仮想通貨が財産にある場合の対応とポイント
仮想通貨(暗号資産)を代理で購入する(してもらう)場合の税金
仮想通貨の購入には手間取ることも多く、知人からビットコインの購入をお願いされたり、反対に購入をお願いすることもあると思われます。
取引を代行した・もしくは代行してもらった場合、どのような対処が必要になるでしょうか?
自分が代行して仮想通貨を取引した場合、取引所等で記録される取引履歴の中に本人の所得計算に関係のない取引の履歴が混ざってしまいます。
そのため、税金計算を行う際は該当する履歴を無視して計算する必要があります。
反対に、第三者に仮想通貨の購入を委託した場合には、その後に当該通貨を売却するなどして利益を生じた場合の利益の計算のために、第三者が購入したときのレートや数量の情報が必要となります。
そのため、代行をお願いした場合は、その第三者から仮想通貨購入時の情報を提供してもらい、保存しておく必要があります。
代行によって税金面で何かしら変化があるということではありませんが、取引履歴の取り扱いについては注意が必要になるという点はしっかり理解しておきましょう。
仮想通貨(暗号資産)の貸し借りがある場合の税金
家族や友人等と仮想通貨の貸し借りをした場合の課税関係はどうでしょうか?
まず、利子を付けて貸し借りをするケースでは、リターンとして受け取る部分に対して税金が貸し手側に発生します。
例えば、1BTCを年利5%で貸し付けた場合、リターンとして0.05BTCを受け取ることができます。この場合、0.05BTCに対して課税されます。
無利子での貸し借りの場合、一見税金がかからないように感じますが、借り手側に贈与税がかかる可能性があります。
これは利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる可能性があるためです。
詐欺等に遭い喪失した仮想通貨(暗号資産)の処理
詐欺等に遭い、本意でなく送金してしまって取り戻せなくなった仮想通貨は、税金額の計算上、損失として扱うことが難しいものと考えられます。
例えば、上で説明したような相対取引において、仮想通貨を送金したにも関わらず、取引相手と連絡が取れなくなり、対価となる通貨等を受け取ることができないといったケースです。
これは、詐欺の被害は雑損控除の対象にはならないためです。
詐欺に遭って仮想通貨を失いつつも、喪失とはならないことを前提に計算される税金を納めることは大きな負担となるため、特に相対取引では、詐欺に遭わないよう細心の注意をすべきでしょう。
まとめ
第三者への贈与、購入の代行、貸し借り、相対取引のケースを検討しましたが、いずれにも共通することは、取引所等の取引履歴に情報が残らなかったり、通常の取引所等での取引履歴と判別困難となったりする、というトラブルが生じうる点にあります。
税金額の計算に必要となる情報を把握しておき、取引の際には適切に情報を取得し、保存しておく必要があるでしょう。