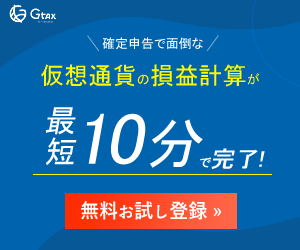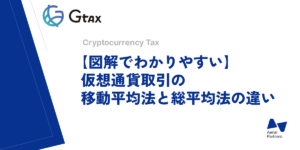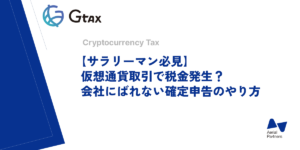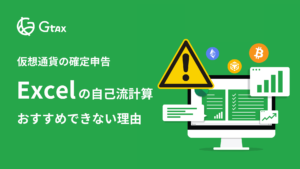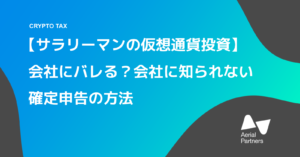暗号資産(以下、仮想通貨)によって利益が出たとき、視野に入れなくてはならないのが確定申告の存在です。
確定申告の手間や複雑さを考えると「専門家である税理士に任せた方がいいのではないか」と考える方も多いでしょう。
本記事では、仮想通貨の確定申告を税理士にお任せした方がいい理由や相場感、自身で確定申告を行う場合のポイントを紹介します。
仮想通貨の確定申告に関する基礎知識
仮想通貨によって利益を得た年は、年間の所得を確定する「確定申告」が必要となるケースがあります。
確定申告とは所得税の支払いに必要な手続きのことで、利益が発生しているのに申告せずに放置するとペナルティが課せられるだけでなく、刑事罰に発展することもあります。
自分が確定申告の対象者であるか、必ずチェックしておきましょう。
仮想通貨に関する所得額は「仮想通貨による総収入額 ー 必要経費」で計算することができます。
ここでいう必要経費とは、仮想通貨の購入費用や勉強のための書籍代、各手数料や取引にかかる通信費などのことです。
仮想通貨の利益が20万円を超えたら「確定申告が必要」
総収入額から必要経費を差し引いた「所得額」が20万を超えたら原則、確定申告が必要となります。
ここで注意したいのは「仮想通貨にはさまざまな使い方がある」という点です。
仮想通貨は売却して日本円を得られるほか、買い物時に通貨として活用できたり、ほかの仮想通貨と交換したりなどといった使い方ができます。
それゆえ日本円に換金されないまま利益を得ているケースがあり、所得の算出方法も少々複雑になりがちです。
仮想通貨による所得は「雑所得」に分類される
所得税には10種類の税区分があり、仮想通貨の所得は「雑所得」に該当します。
雑所得は給与所得と合算して計算される税区分で、例えばサラリーマンとしての給与所得が400万円、仮想通貨の所得が200万円だとすると、600万円が控除前の所得となります(総合課税)。
また、総合課税は累進課税制度で税率が決まります。
累進課税制度とは、所得が大きいほど税率もあがっていく制度のことです。
つまり仮想通貨の所得が大きくなればなるほど税率が上がるため、多くの税金を支払う必要があります。
仮想通貨の確定申告を税理士に丸投げしたほうがよい理由
仮想通貨の所得計算はほかの投資商品と違う面があるため、税理士に任せることで複雑な計算の手間を省くことができます。
では、どのような点で通常の確定申告と異なり、複雑なのでしょうか。
ここからは、仮想通貨の確定申告を税理士に丸投げした方がよい理由を紹介します。
仮想通貨の課税タイミングが複雑であるため
例えば、FXは含み益を確定する(日本円を得る)ことで利益となりますが、仮想通貨の決済方法は含み益の確定だけではありません。
仮想通貨の決済方法は多様であるため、課税されるタイミングにも複数のパターンが存在します。
課税されるタイミングには、以下のようなパターンがあります。
- 仮想通貨で商品・サービスを購入したとき
- 仮想通貨でほかの仮想通貨を購入したとき
- マイニングやステーキングの報酬、レンディングの利子などにより仮想通貨を取得したとき
- 仮想通貨の分裂(分岐)にともなって、新たに誕生した仮想通貨を売却(使用)したとき
仮想通貨で取引できる企業は日本にも複数存在し、仮想通貨でサービスや商品を購入することもできます。
このとき日本円は取引に介在していないものの、サービスや商品を得ている時点で利益が発生していると考えられるため、所得税の観点では「日本円に換金した」ことと同じ扱いになります。
結果「購入金額から仮想通貨の取得金額を差し引いた額」を所得額として計算しなくてはなりません。
また「ほかの仮想通貨を購入したとき」、例えばビットコイン(BTC)を使ってイーサリアム(ETH)を購入したときは、イーサリアムの購入価格(時価)からビットコインの取得額を差し引いた額が所得として計算されます。
このように、自身が行う仮想通貨の取引方法が多様であるほど「いつどこで、どのように使用したか」「当時のレートは」など確認する情報が多く、手続きが煩雑になりやすいといえます。
税の専門家である税理士に計算を丸投げした方が手間もかからず、ミスも置きにくいと考えられるでしょう。
仮想通貨の課税タイミングについてはこちらでも解説しています。
税金の計算方法が「総平均法」と「移動平均法」の2種類があるため
仮想通貨では所得額の算出に使われる「取得価格」の計算には「総平均法」と「移動平均法」の2種類があります。
仮想通貨を売却して日本円に換金するとき、所得額は以下のような計算式で算出されます。
所得額=売却額-(※取得価額×売却数量)
上記の「取得価額」を割り出す方法が総平均法と移動平均法です。
この取得価額は「仮想通貨を購入したときの額」ではないため、留意しておきましょう。
原則として、個人が所得税を算出するときに使用する方法です。
1年間で購入した仮想通貨の取得価格を、1年間に保有した仮想通貨の数で割って計算します。
保有している仮想通貨の平均価格を出すのが、総平均法です。
原則として、法人が法人税(所得税)を算出するときに使用する方法です。
仮想通貨を新規で取得するたびに平均値を算出します。
例えば200万円、300万円の通貨を1通貨ずつ保有すると、平均価格は250万円(※1)となります。
この後400万円の仮想通貨を1通貨購入すると、平均は300万円(※2)となります。
このように購入するたびに平均値を再計算する方法が移動平均法です。
算出方法は税務署に届出を出すことで切り替えることができ、切り替えることで節税になる場合もあります。
とはいえ計算や手続きも含めて複雑になりやすいため、税理士に任せた方が安全と言えるでしょう。
仮想通貨の税金についてはこちらで詳しく解説しています。
仮想通貨ならではの税金対策があるため
仮想通貨には利益を「圧縮」、つまり全体の利益を減少させて課税所得を低くすることで、納税額を減らせるケースがあります。
そのキーとなるのが、含み損と含み益です。
例えば、含み損は決済することで損失を確定させることができます。
損失を確定させると別の仮想通貨で利益が出ていた場合でも損益を相殺できるため、課税所得を減らすことができます。
- 100万円で購入したBTCが50万円まで下がった(50‐100= -50万円)
- 今年の利益額が200万円
- 含み損を確定させることで200-50=150万円となり、課税所得額が減少
しかしながら、課税所得は総平均法や移動平均法を用いて算出されているため、買戻しなどを行うと、購入時の価格(100万円で購入)を適用するといった単純な計算を当てはめることができません。
また含み益を決済することで節税になるケースもあります。
いずれにしろ専門知識を有する税理士ならこのような節税対策に気付きやすく、また今保有している仮想通貨の扱いについても相談できるため、迷わずに確定申告を進めることができるでしょう。
仮想通貨の確定申告を税理士に丸投げする際の費用
税理士に確定申告の処理を依頼すると、当然ながら費用がかかります。
税理士に丸投げ、つまり記帳代行までお願いした場合の相場は総額8万円〜25万円ほどです。
しかし、実際には取引内容や件数によって追加のオプション費用がかかることが多いです。
特に過去年度の計算が必要な場合は一気に費用が膨れ上がってしまう可能性もあります。
取引件数や利益額、自身の手間などを考えたうえで依頼をするか決めていきましょう。
また税理士や税理士法人ごとに得意分野があるため、仮想通貨に明るい税理士に依頼するのがおすすめです。
仮想通貨の確定申告を自分で行う場合のポイント
仮想通貨の利益額が少額の場合は、税理士に依頼をすることで利益がマイナスになってしまうこともあります。
自分で確定申告をすると手間がかかりますが、その分の費用を浮かせることができ、一長一短と言えるでしょう。
そこで今回は、自分で確定申告を行った場合のポイントを紹介します。
仮想通貨取引所での取引履歴を保存しておく
年が明けたら、確定申告の書類を用意する前に、前年の仮想通貨の取引履歴を保存しておきましょう。
仮想通貨の納税額は取得価格によって計算されるため、取引履歴が必要な情報となるからです。
取引履歴は仮想通貨取引所のサイトから確認できます。
ダウンロードしてフォルダにまとめておくと、記帳の際にアクセスしやすくなるのでおすすめです。
複数の取引所を使用しているのであれば、全取引所の履歴を保存しておく必要があります。
また、仮想通貨で買い物をした場合の領収書も、同様に保管しておきましょう。
仮想通貨の確定申告に特化したツールを使用する
仮想通貨の確定申告は複雑かつ煩雑になりがちです。
しかし、専用のツールを使えば損益の計算を簡単に行うことができ、作業の手間を省けます。
Gtaxは、取引データをアップロードするだけで面倒な損益計算を自動化できるため、確定申告の複雑な計算の負担を軽くすることができます。
また会計ソフトと連携することで、自宅PCから確定申告書類を提出できるケースもあります。
専用ツールを使わない場合は、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ツールを使用するとよいでしょう。
なお、電子申告にはマイナンバーカードや利用者識別番号などが必要です。事前に用意しておきましょう。
早めに確定申告の準備を進めておく
確定申告の受付期間は、毎年2月16日〜3月15日になります。
確定申告ではデータの準備や計算、書類の作成に時間がかかるのはもちろん、受付期間中は税務署が混みあい連絡がつきにくくなる可能性があります。
また電子申告の際は、マイナンバーカードや利用者識別番号を所持する必要があるため、未所持の方は申告までに準備をしておく必要があります。
また既に所持している方でも、パスワードを失念した場合には再発行手続きが必要です。
このように、確定申告の準備はさまざまな要因で時間がかかってしまうことがあります。なるべく早めに準備をし、時間にゆとりを持って進めていきましょう。
まとめ
仮想通貨の所得はほかの投資商品に比べても計算が難しく、用意する書類も多数あります。
税理士に依頼すれば複雑な計算の代行はもちろん、記帳や確定申告書の作成まで任せることができます。
とはいえ取引データなどは自分で用意する必要があるため、日頃から準備しておくと安心です。
ツールを使えば少ない費用で計算できる場合もあるため、自身に合った方法を検討してみてください。