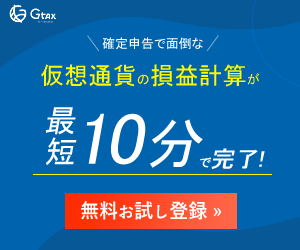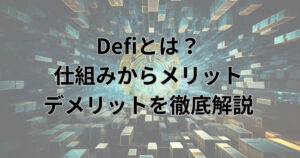「ビットコインを買ってみたいけれど、なぜ価値がついているのかがよくわからない」「取引はしているものの、実はどういう通貨なのか詳しくは知らない」という方も多いのではないでしょうか。
ビットコインは、2009年に誕生した世界初の暗号資産(以下、仮想通貨)であり、2025年現在でおよそ16年が経過するという長い歴史をもっています。
この記事では、ビットコインの歴史や仕組み、ビットコインを持つメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
もっともメジャーな仮想通貨「ビットコイン」とは
ビットコインは仮想通貨のひとつで、デジタル通貨に分類されます。
デジタル通貨とは、紙幣や硬貨の形ではなく、インターネット上のデータとしてやり取りされるお金のことをいいます。
日本円や米ドルなどの法定通貨は国や中央銀行が発行して管理しますが、ビットコインのようなデジタル通貨は国や中央銀行ではなく、インターネット上の仕組みで管理されているのが特徴です。
仮想通貨は他にも、イーサリアムやリップルなどさまざまな種類がありますが、ビットコインは世界で最初に誕生した仮想通貨ということもあり、もっとも広く知られています。
ビットコインの概要
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 名称 | ビットコイン(BTC) |
| 現在の価格 | ¥17,300,971(記事執筆時) |
| 発行上限枚数 | 2,100万枚 |
| 現在の時価総額 | ¥345,417,230,789,232(記事執筆時) |
| コンセンサスアルゴリズム | プルーフ・オブ・ワーク(PoW) |
| 現在の主な用途 | 国際送金、商品の決済手段など幅広く活用 |
ビットコインは、0.5BTCや0.001BTCなど細かな数量でも購入できるため、少額でも入手できる点が特徴です。
知っておきたい「ビットコインの歴史」
ビットコインは、2009年に誕生し、2025年現在でおよそ16年が経過しています。
ここでは、仮想通貨の中でも長い「ビットコインの歴史」について紹介します。
2009年:ビットコインの運用が始まる
ビットコインは、2008年に「サトシ・ナカモト」と名乗る人物がインターネット上に投稿した論文をきっかけに開発されました。
その後、2009年1月に世界で最初のブロック(Genesis Block)が生成され、ビットコインの運用がスタートします。
| 年月 | できごと |
|---|---|
| 2008年10月 | サトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto)がビットコインの仕組みをまとめた論文を公開 |
| 2009年1月 | 世界で最初のブロック「Genesis Block」が生成される |
| 同年1月 | ビットコインの初送金 |
今では広く知られているビットコインですが、当初はまだ仮想通貨としての価値が認められておらず、一部の技術者の間で試されるだけの存在でした。
そのため、ビットコインの初送金は、サトシ・ナカモトから主要開発者であるHal Finney(ハル・フィニー)氏への50BTCの送金だったといわれています。
その後、ビットコインは徐々に注目を集め、翌年2010年には初めて実物商品(ピザ)との交換が行われました。
| 年月 | できごと | 1BTCの価格 |
|---|---|---|
| 2010年5月 | ビットコインを利用した取引が初めて成立 | 約0.2円 |
| 同年7月 | 世界初のビットコイン取引所「Mt GoX」がサービスを開始 | 約7円 |
初めての取引は2010年5月22日、ビットコイン1万枚とピザ2枚を交換するというものでした。
以降、5月22日は「ビットコイン・ピザ・デー」と称して、イベントや割引などが開催されています。
2011年:初めてのビットコイン急騰、そして急落
運用当初は価値が認められていなかったビットコインですが、2011年に入ると注目度はさらに増し、それに伴って価格も急騰していきます。
| 年月 | できごと | 1BTCの価格 |
|---|---|---|
| 2011年3月 | 日本のTibanne社が「Mt.Gox」を買収し、価格上昇 | 約70円 |
| 同年4月 | 米タイムズ誌で特集され知名度拡大。価格上昇 | 約80円 |
| 同年6月 | ビットコインが急騰し、一時31ドルに達する | 約3,100円 |
| その後すぐ | Mt.Goxがハッキングを受け、価格下落 | 約1,400円 |
| 同年 | 1 BTC = 2ドル台まで急落し、バブル崩壊 | 約160円 |
| 同年年末 | 1 BTC = 3ドル~4ドルぐらいまで戻る | 約300円 |
2011年初めに1BTC = 1ドル前後(100円前後)だったビットコイン価格は、6月には一時31ドル(約3,100円)まで急騰しました。
しかし、その後すぐにハッキング被害などの影響で価格は2ドル台(約160円)まで急落します。
その後は少しずつ回復し、2011年末ごろの価格は3〜4ドルほど(約300円)となっています。
2013年:日本国内でもビットコインが人気に
2013年には、ビットコインは世界中で注目を集め、日本国内でも利用者が増えました。
この背景には、3月に欧州のキプロス共和国で起きた金融危機(キプロス危機)が関係しているといわれています。
キプロス危機とは、キプロスの銀行が経営危機に陥り、預金封鎖が行われた出来事のことです。
預金を引き出せなくなったことで中央銀行に対する信用が低下し、資産を守る手段として、銀行などの管理主体をもたないビットコインが再び注目されました。
その結果、法定通貨をビットコインに交換する人が増え、価格は大きく上昇します。
| 年月 | できごと | 1BTCの価格 |
|---|---|---|
| 2013年3月 | キプロス危機の影響で注目度が高まり価格上昇 | 約5,000円 |
| 同年12月 | NHKで特集され、日本でも知名度拡大し価格急騰 | 約12万円 |
| 同年12月 | 中国政府が銀行など金融機関にビットコイン関連サービスの禁止を発表し、価格下落 | 約8万円 |
2017年:「仮想通貨元年」を牽引
2014〜2015年は、Mt.Goxをはじめとする取引所でハッキング被害が相次ぎ、価格は急騰と急落を繰り返しました。
しかし、2016年になると徐々に回復し、価格も上昇傾向となります。
そして2017年には仮想通貨市場が一気に盛り上がり、「仮想通貨元年」と呼ばれました。
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2014年~2015年 | Mt.Goxをはじめとする取引所でハッキング被害が相次ぎ、価格乱高下 |
| 2016年 | ゆるやかに回復。法整備の準備も進む |
| 2017年 | 日本でも法整備(改正資金決済法)が本格化する仮想通貨市場が急騰し、「仮想通貨元年」と言われる |
日本でもビットコインの知名度がさらに高まり、仮想通貨に関する法整備(改正資金決済法)が進みました。
その結果、個人投資家が急増し、価格も急騰します。
ビットコインの価格は、11月末に初めて1万ドル(約120万円)を突破すると12月はさらに勢いを増し、2万ドル近く(約220万円)を記録しました。
2021年:企業のビットコイン購入が相次ぎ、過去最高値を記録
2021年には、米テスラをはじめとする企業のビットコイン購入が相次ぎ、機関投資家の参入も加わって価格が急騰しました。
| 年月 | できごと | 1BTCの価格 |
|---|---|---|
| 2021年2月 | テスラが15億ドル(約1600億円)相当のビットコインを購入 | 約500万円 |
| 同年4月 | コインベースがナスダックに上場 | 約700万円 |
| 同年6月 | エルサルバドルでビットコインが正式な法定通貨になる | 約500万円 |
| 同年10月 | アメリカで初めてビットコイン先物ETFが承認される | 約730万円 |
| 同年11月 | ビットコインの価格が過去最高値を記録する | 約780万円 |
4月には、米コインベースがナスダックに上場した影響もあり、1BTCが当時過去最高値となる約6万4千ドル(当時のレートで約700万円)を記録しています。
5月に中国のマイニング規制やテスラ騒動などがあり一度大きく下落しますが、再び回復し、11月にはビットコイン価格が約6万9千ドル(約780万円)に達しました。
その後もビットコインは急騰と急落を繰り返しながら緩やかな価格推移を続け、2024年にはついに円建てで初めて1,000万円台を突破しました。
ビットコインの仕組みや特徴
冒頭でお伝えしたように、ビットコインはデジタル通貨のため、国や銀行のような「お金を一か所で管理する組織」がありません。
代わりに、世界中の参加者でお金の記録を確認し合いながら管理しています。
ここでは、ビットコインの仕組みや特徴をわかりやすく解説します。
ビットコインの取引発生・成立の流れ
ビットコインの取引は、中央管理者を通さず、世界中の参加者同士が直接やりとりする仕組み(P2Pネットワーク)で行われます。
- 取引相手にビットコインを送金すると、取引情報がネットワーク上にいるすべてのマイナー(取引を確認してブロックをつくる人やコンピューター)に送信される
- 取引情報を受信したマイナーは、未処理の取引をまとめて「ブロック」と呼ばれるデータの箱に入れる
- 2でまとめられた箱が「新しいブロック」として作られ、ネットワーク上に追加される取引が正式に記録され、取引成立
取引情報には、「誰が誰にいくら送金したか」といった情報のほか、本人が取引を行った証明となるデジタル署名などが含まれています。
マイナーは、世界中の誰でも参加可能であり、多くの個人や企業が分散して動かしています。
銀行の代わりに世界中の何千台ものパソコンがみんなで取引を確認している状態のため、「一か所のサーバーをハッキングしたら全部アウトになる」という事態は起きません。
マイナーによって作られた「ブロック」は、鎖のようにつなげて記録・保存されていきます。
これが「ブロックチェーン」と呼ばれる仕組みです。
ブロックチェーンで作られた取引記録は、ネットワーク全体で共有・管理されているため「分散型台帳」とも呼ばれています。
取引に欠かせない「プルーフ・オブ・ワーク(PoW)」
プルーフ・オブ・ワーク(以下、PoW)とは、マイナーがブロックを作るために複雑な計算問題を解き、ブロックチェーンに間違った取引が記録されないようにする仕組みです。
上述したとおり、ビットコイン取引は誰でも参加できる仕組みとなっています。
また、ブロックチェーンには銀行でいうところの台帳の役割もあるため、ウソの取引データが勝手にブロックチェーンに記録されないよう注意しなければなりません。
そこで、間違った取引が記録されないよう作られた仕組みがPoWです。
ブロックには条件つきのハッシュ値があり、マイナーはその条件を満たすハッシュ値が見つかるまで、何度も繰り返し計算します。
最初に見つけたマイナーがブロックを作る権利を得て、周囲から「確かに正しい計算をした」と承認されることで、ブロックチェーンに追加されます。
PoWでは、「条件を満たすハッシュ値を見つけて承認されたマイナーしかブロックを追加できない」仕組みにすることで、ビットコイン取引の安全性を保っています。
ビットコインを取引以外で得る方法「マイニング」
ビットコインは売買取引のほか、「マイニング」でも得られます。
マイニングとは、企業や個人の「マイナー」がPoWの計算を解いてブロックを作ることを指し、新しいビットコインを報酬として得ることができます。
取引にはPoWが欠かせません。
また、マイナーが増えれば増えるほど、データ改ざんなどの抑止となり、安全性の維持につながります。
そのため、世界中の人々や企業がマイニングに関わっています。
ビットコインの「ハードフォーク」とは
ハードフォークとは、簡単にいうと「通貨の分裂」です。
ビットコインなどの仮想通貨は、共通のルール下で動いています。
しかし、ときに開発者や参加者の意見が分かれ、ルールを変更する必要が出てくるケースがあります。
仮に「新しいルールに変えたい」となった場合、古いルールと新しいルールを両立させることはできません。
その結果、ブロックチェーンが分岐することがあります。
これをハードフォークと呼びます。
ハードフォークが起きると、新しい仮想通貨が生まれることがあります。
実際、2017年に誕生した「ビットコインキャッシュ(BCH)」は、ビットコインから分岐して生まれた通貨であり、元々のビットコインとはルールが異なるものです。
ビットコインを持つメリット
ビットコインには、将来的な値上がりが期待できるだけでなく、中央管理者がいないことによって自分で資産を守れるなど、持つことで得られるさまざまなメリットがあります。
ここでは、ビットコインを持つことで得られる代表的なメリットを3つ紹介します。
将来的な値上がりが期待できる
1つ目は、将来、価格が上昇する可能性がある点です。
ビットコインは、発行できる枚数があらかじめ2,100万枚と決められており、それ以上増やすことができません。
そのため、欲しい人が増えれば増えるほど価値が高まり、価格も上がりやすいといわれています。
これまでもビットコインの価格は大きく変動しながらも、長期的には上昇傾向を示してきました。
今後どこまでの値上がりが期待できるかは誰にもわかりませんが、需要が高まるほどに価格への影響は大きくなると考えられるでしょう。
国や銀行に資産を管理されず、自分で守れる
2つ目は、自分の資産を自分で守れる点です。
銀行に預けている預金は、国や金融機関によって管理されています。
万が一、国の政策で預金封鎖が行われたり、インフレによって通貨の価値が下がったりすると、大切な資産が目減りする可能性があります。
一方、ビットコインには銀行のような中央管理者が存在しません。
秘密鍵(パスワード)を自分で管理していれば、外部の影響を受けにくく、自分の資産を自分で守ることができます。
こうした特徴から、ビットコインは「デジタルゴールド」とも呼ばれ、価値の保存手段として注目されています。
投資や資産運用以外の使い道もある
3つ目は、投資以外にも使い道がある点です。
ビットコインと聞くと、投資や資産運用をイメージする方も多いかもしれませんが、実際には決済手段としても利用できます。
たとえば、一部の店舗やオンラインショップでは、「ビットコインで商品やサービスを購入する」といったことが可能です。
また、送金にも活用できます。
ネットワーク上で直接送金できるため、従来の方法よりも速く手数料を抑えて送金できるほか、24時間365日いつでも送れるところもメリットといえるでしょう。
ビットコインを持つデメリット・注意点
ビットコインにはさまざまなメリットがありますが、注意しておきたいポイントもあります。
ここでは、ビットコインを持つデメリットや、知っておきたい注意点を3つ紹介します。
価格の変動が大きく損をする可能性がある
まず挙げられるのは、価格の変動が激しく、損をする可能性がある点です。
ビットコインは、株式以上に価格の振れ幅が大きいことで知られており、1日のうちに乱高下を何度も繰り返すことがあります。
そのため、損失が生じるリスクは避けられません。
投資全般にいえることですが、損をする可能性があることを理解したうえで、自己責任で取引を行いましょう。
秘密鍵を紛失すると取り戻せない
秘密鍵というパスワードをなくしてしまうと、資産を取り戻せない点もデメリットといえます。
たとえば銀行預金の場合、万が一「パスワード忘れた!」となっても、本人確認を行えば銀行から再発行してもらえます。
一方、ビットコインの場合はパスワードを忘れても誰も再発行してくれません。
秘密鍵がなければ誰も復元できず、資産にアクセスできなくなってしまいます。
大切な資産を守るためにも、秘密鍵の管理には十分注意しましょう。
確定申告の手間がある
仮想通貨取引で利益が出た場合は、確定申告が必要です。
取引回数が多かったり、取引履歴をきちんと保管していなかったりすると、あとで計算が大変になり手間がかかります。
利益を少なく申告したり、「バレないだろう」と思って申告しなかったりすると、ペナルティが科される可能性もあります。
日頃から取引履歴をしっかり保管し、利益が出た際には早めに確定申告の準備をしておきましょう。
ビットコインに関する「よくある質問」
ここでは、ビットコインに関する「よくある質問」を紹介します。
- ビットコインと電子マネーの違いは?
-
ビットコインはインターネット上でやりとりされるデジタル通貨です。
国や銀行は管理しておらず、取引や管理はインターネット上で行われます。一方の電子マネーは、円などの法定通貨を電子データ化したものです。
企業や銀行が管理しており、現金支払いの代わりに使うことができます。 - ビットコインを現金に換える方法は?
-
ビットコインは、仮想通貨取引所または販売所で売却することで、現金に交換できます。
取引所の口座にビットコインを送金し、売却後に現金を自分の銀行口座へ振り込む流れが一般的です。 - ビットコイン取引はどうやって始める?
-
まずは仮想通貨取引所で口座を開設します。
本人確認が完了したら、日本円を入金することでビットコインを購入できます。取引所によって扱っている通貨や手数料が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
まとめ
ビットコインは世界で最初に誕生した仮想通貨であり、将来的な値上がりが期待できる資産として注目されています。
国や銀行などの中央管理者はいませんが、取引情報の確認やデジタル署名、マイナーによる複雑な計算(PoW)といった仕組みにより、安全性が保たれています。
とはいえ、ハッキング被害のリスクや損をする可能性はゼロではありません。
これからビットコインを始めようと思っている方は、取引所の選び方や税制などの情報を集め、余剰資金の範囲で無理なく始めましょう。