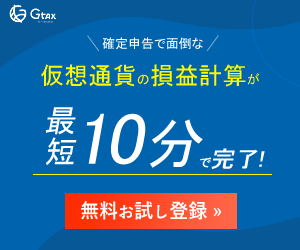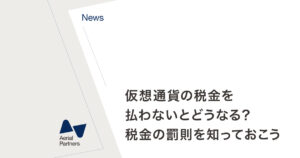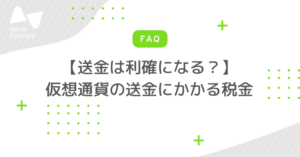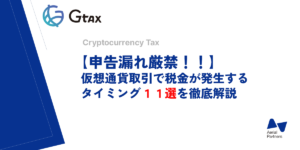暗号資産(以下、仮想通貨)で20万円超の利益が出ると、確定申告が必要となります。
しかし、現在保有している仮想通貨を確定せずに年をまたいだ場合、前年分の税金はどのように計算されるのでしょうか。
本記事では仮想通貨を「年またぎ」で保有し続けたときの税金の考え方や、年またぎをすることによるメリットやデメリットを、ケーススタディを交えて解説します。
仮想通貨の利益を年またぎで確定するとどうなる?
仮想通貨特有の税金について語る前に、まずは確定申告についておさらいしましょう。
確定申告とはある一年間の所得税を支払うためのもので、その年に一定以上の所得を得た人が対象となります。
確定申告は翌年の2月16日〜3月15日の間に行う必要があり、この期間中に確定申告の書類を揃えて、税務署に直接もしくはインターネット(e-tax)で申告手続きを行うことになります。
税務署はここで伝えた所得額を元に「所得税」や「住民税」を算出し、私たちの支払う納税額が決まります。
給与だけをもらっている人の場合は確定申告の必要がありませんが、もし仮想通貨による副業などで20万円以上の所得がある人は確定申告の対象となります。
そのため、年内に損益を確定させた方が良いのか、それとも年をまたいである程度持ち越した方が良いのか、確定申告が必要となるか否かがひとつの判断基準になることもあります。
仮想通貨の所得は「損益が確定した時点」で発生する
仮想通貨で得た収益も、所得税や住民税の対象となります。
仮想通貨には「含み損益がでているとき」と「ポジションを決済し、損益を確定させたとき」の2つの状態がありますが、確定申告においては後者「損益を確定させたとき」に「所得が発生した」と捉えられます。
つまり、当年(例:2024年)から保有している仮想通貨を翌年(例:2025年)決済した場合、その損益は2025年のものと考えられるため、2024年の所得を申告する今年の確定申告に含める必要はありません。
年をまたいで決済した損益は、再来年(例:2026年)の確定申告時に記載することとなります。
仮想通貨の損益を年またぎで確定させた際の税金計算例
では仮想通貨の損益を年またぎで確定させると、税金はどのような計算になるのでしょうか。
含み損がでているとき、含み益が出ているときを例を挙げて解説します。
【前提】仮想通貨の取得価額は翌年に引き継ぐ
仮想通貨にかかる税金を算出するためには「所得」の計算が必要です。
仮想通貨の所得額は以下のように計算されます。
所得額=売却額-(取得価格×売却数量)
ここで、取得価額とは、仮想通貨を購入した時の価格のことです。
年またぎで仮想通貨を持ち越すと、この取得価格も翌年に引き継ぐことになります。
投資家のAさんは2024年にビットコインを100万円で購入し、決済をせず2025年に持ち越しました。
また2024年には、50万円で2つ購入(合計100万円)したイーサリアムが200万円になっており、利益を確定しました。
上記のような条件を計算に当てはめると、2024年の所得は200-(50万円×2)=100万円となります。
2024年にビットコインを買っているものの決済はしていないため、2024年の所得には含まれません。
ただ、この2024年に得たビットコインの取得価額「100万円」は決済するまで引き継がれることになります。
翌年以降に決済したときには、こちらの取得価額を基に損益を計算するため、忘れないようにする必要があります。
赤字になっている仮想通貨を年またぎした場合
赤字、つまり含み損が出ている仮想通貨を年またぎした場合、前年に他の利益が出ていたとしてもその利益とは相殺できません。
一方で年またぎしたポジションを決済した場合は、決済した年の利益と相殺することができます。
ケーススタディとして、イーサリアムの収益がありながらもビットコインの含み損を持っている例を時系列で考えてみましょう。
なお分かりやすくするため、含み損は変動しないものとしています。
- 2024年
-
イーサリアムを売却して得た収益(100万円)、ビットコインは決済せず含み損(-100万円)を抱えた状態とする。
- 2025年
-
2月:2024年内にイーサリアム(100万円)の売却益に関する確定申告を行い、税金を支払う。
4月:新たにリップルを50万円で購入する。
5月:リップルを100万円で決済(+50万円)する。
6月:ビットコインの含み損を決済(-100万円)し、以降取引をせずに年度を終わる。 - 2026年
-
2月:確定申告をするが、リップルの利益をビットコインの損失が相殺されているため、マイナスの所得として税金の支払いはなし。
このように、2024年度の確定申告(2025年2月)はイーサリアムの売却で得た収益100万円分の所得があるために税金を支払っていますが、2025年度の確定申告においては、年またぎで持ち越したビットコインの損失が大きかったため、所得がマイナスとなって税金の支払いがなくなりました。
もし2024年度のうちにビットコインの損失を確定させて所得をゼロとしていれば、2025年度はリップルの売買で得た50万円の収益にのみ税金がかかるため、上記ケーススタディよりも税金を抑えることができました。
年内に大きな額の収益が出ている場合は、あえて含み損を年またぎせず年内で決済させると損失として差し引くことができるため、所得額が減って節税効果が期待できます。
黒字になっている仮想通貨を年またぎした場合
黒字、つまり含み益のある仮想通貨を年またぎした場合についても考えてみましょう。
前述の通り、税額計算における仮想通貨の損益は「決済時」に数えられます。
これは含み益の出ている仮想通貨を「年またぎ」した場合も同様です。
つまり、多くの利益が発生した年に含み益を決済せず年またぎすると、納税額の引き下げを期待することができます。今回も例を交えて見てみましょう。
例えば、イーサリアムで300万円の利益があり、また400万円の含み益があるビットコインのポジションがあるとします。
上記のようなケースを考えたとき、保有中であるビットコイン(400万円)の決済時期には2つの選択肢があります。
今年にするか、それとも来年以降にするか、です。
今年中に決済をすると決めた場合、今年の利益は合計700万円となります。
一方で、決済時期を来年以降にすると今年の利益はイーサリアムのみ(300万円)となるため、決済するかしないかで金額が大きく変わります。
仮想通貨は累進課税を導入しており、所得が高くなればなるほど税率も上がります。
黒字の大きい年は含み益のポジションを翌年以降に持ち越すことで所得額を増やさずに済むため、節税効果につなげることができます。
一方で、年内に大きな赤字が出ている場合はあえて決済することで損益を相殺し、翌年以降にかかるはずだった所得額を引き下げることができます。
仮想通貨の確定申告までに実施すべきこと
毎年2月16日〜3月15日には確定申告があります。
今持っているポジションを年またぎするかどうかを検討したあとは年内の所得額を計算し、申告書類を揃えて提出しなくてはなりません。
そこで今回は、確定申告までに実施しておきたいことを5つ紹介します。
仮想通貨取引所での取引履歴を全件保存しておく
仮想通貨の税金計算では決済利益の額だけでは無く取得価額も必要となるため、仮想通貨の確定申告では取引履歴を全件保存しておきましょう。
ここで注意したいのはポジションを数年間「年またぎ」すると、取得価格が記載されている取引報告書も数年前のものとなる点です。
Web交付の取引報告書は多くの場合5年程度保存されますが、それ以前の情報は直接証券会社に取り寄せなくてはならないこともあります。
取引報告書は全件ダウンロードをして保存し、自身で管理するようにしましょう。
仮想通貨取引にかかる経費を計算しておく
仮想通貨の取引にかかる経費は、仮想通貨の利益から差し引くことができます。
経費を計上することで納税額を減らすことができるため、対象となる経費を計算しておきましょう。
仮想通貨にかかる経費の例には、以下のようなものがあります。
- 出金手数料
- 取引手数料
- 仮想通貨関連のセミナー代
- 仮想通貨関連の書籍
- パソコン代(※10万円以上で減価償却対象)
- ネット通信費(※按分対象)
ただし領収書の保管が必要なため、経費として計上する場合は必ず取っておきましょう。
仮想通貨の税金計算の方法や利益に当たる取引を知っておく
仮想通貨の税金計算は複雑で、暗号資産特有の「取得価格の計算方法」と「利益計上のタイミング」があります。
取得価格は2種類の方法で計算される
仮想通貨の所得額は得た利益(損失)から取得価格を差し引いて計算されます。
この取得価格の計算方法には「移動平均法」と「総平均法」の2つ方法があるため、覚えておきましょう。
なお、届け出をしない限りは原則「総平均法」を用いることとしており、「移動平均法」を用いての計算で確定申告を行う場合は別途手続きが必要になります。
最終的な損益は一致することになりますが、年度ごとの損益額やそれぞれの計算方法による分かりやすさ・手間などのメリットとデメリットがあるため、どちらを用いた方が良いかは取引状況によって判断すると良いでしょう。
仮想通貨の税金の詳しい計算方法についてはこちらで解説しています。
利益計上のタイミングにも複数ある
仮想通貨に対応しているお店では、仮想通貨を「通貨」として商品やサービスの購入に使うことができます。
しかし、税法上では取引を行った時点で「利益を得た」として見られるため、利益として計上しなくてはなりません。
他にも、下記のようなタイミングでも損益が確定したとみなされ、計算上組み込まなければいけません。
- 仮想通貨でほかの仮想通貨を購入したとき
- マイニングやステーキングの報酬、レンディングの利子などにより仮想通貨を取得したとき
- 仮想通貨の分裂(分岐)にともなって、新たに誕生した仮想通貨を売却(使用)したとき
確定申告では上記を踏まえて準備する必要があるため、自身の取引にあわせて明細書の準備や計算が必要となります。確定申告の作業が煩雑になりやすい箇所なため、前提知識を身につけておくことが大切です。
仮想通貨の課税タイミングについてはこちらでも解説しています。
税金計算ツールを利用する
前述の通り、仮想通貨の税金計算は複雑であり、自分で計算をすると多大な時間がかかってしまうことがあるため、税金計算ツールや会計ソフトを使用するとよいでしょう。
例えば仮想通貨の損益計算ソフト「Gtax」では、取引データをアップロードするだけで、面倒な損益計算を自動で行うことができます。
会計ソフトとも連携できるので、確定申告の複雑な計算の負担を軽くすることが可能です。
自分で計算する手間を省きたいなら、このようなツールを積極的に利用することをおすすめします。
ふるさと納税を実施する
仮想通貨の利益額が多い年は、ふるさと納税を実施する手もあります。
ふるさと納税とは、自分が選んだ各自治体に寄付をする制度です。
その金額に応じて納税額の控除が受けられるだけでなく、返礼品として特産物などを受け取れます。
家計にもプラスになる点が大きな魅力でしょう。
まとめ
仮想通貨は決済した時点で収益の対象となります。
そのため、年をまたいだ場合は前年の収益には含まれず、確定申告の対象とはなりません。
また、含み損益の決済タイミングをコントロールすることで、ある程度納税額もコントロールすることができます。
とはいえ仮想通貨の価値は変動するため、必ずしも思った通りに節税できないケースもあります。
仮想通貨の税制は複雑なため、計算ツール等の力を借りつつ、場合によっては税理士等の専門家に相談することも検討してみてくださいね。